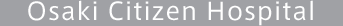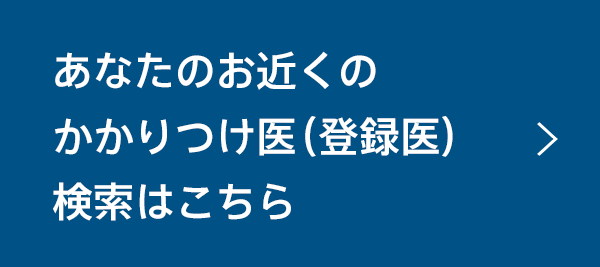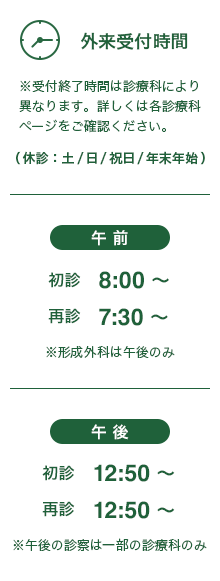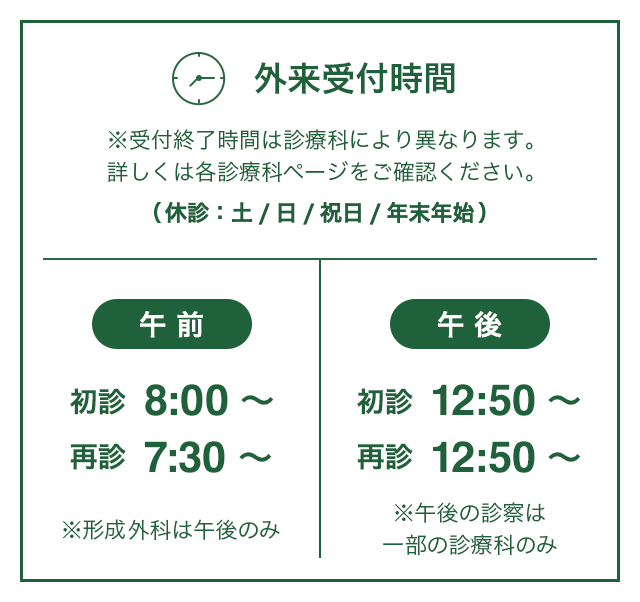糖尿病代謝・内分泌内科
外来担当医表
医師の紹介
診療の概要
糖尿病代謝・内分泌内科では、糖尿病、脂質異常症、高度肥満など、食事や生活習慣と密接に関わる代謝疾患および下垂体・甲状腺・副甲状腺・副腎などの内分泌異常に関わる疾患の精査と治療に取り組んでいます。
診療の特色
糖尿病や脂質異常症、高度肥満は、日常生活が治療の場であり、患者さん自身も主治医チームの一員です。健康寿命を延ばしたり治療効果を高めたりするために、日常生活を送る上で患者さんをどのようにサポートしていけばよいかについて、看護師・管理栄養士・薬剤師などとも協力しながらコーディネートしていくことが大切と考えています。
内分泌疾患は、体内で微細な調節がされているはずのホルモン・ミネラルのバランスが崩れることにより起こりますが、その変化は他疾患が原因となっていると誤認されることも多く、患者さん自身も変化を自覚していないことが少なくありません。身体所見や病歴・採血から内分泌疾患が疑われたときには、ホルモン値の測定や負荷試験・画像検索などを適切な条件下で施行し、正確に責任ホルモンを想定した上で、診断・治療を行うとともに、シックデイなど非常時の管理・指導を行っていくことが大切と考えています。
入院については、以下のようなプログラムで対応します。
血糖マネージメント入院
食事・運動療法を学習し、薬物療法の調整も行う入院です。クリニカルパスを使用し、8日間コースで行っています。
血糖プロファイル改善入院
血糖コントロールが難しい症例に対し、栄養・運動療法の再指導を行ったり、治療方法の調整を行ったりします。インスリン導入を目的とした入院も行っています。
検査・治療入院
血糖や脂質・BMI・内分泌疾患悪化の原因や合併症の検査を行います。その上で、適切な治療法を検討し開始することで、状態改善をはかります。
なお、病診連携のもと、院外から紹介された患者さんは、病状が改善した後、原則として紹介元の病院や医院に戻って治療を続けていただきます。
代表的な疾患と症状
疾患
1型糖尿病、2型糖尿病、脂質異常病、高度肥満、低血糖症、妊娠糖尿病、薬剤性糖尿病、下垂体機能亢進、下垂体機能低下症、下垂体炎、バセドウ病、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能低下症、クッシング症候群、副腎不全、原発性・偽性アルドステロン症、褐色細胞腫など
症状
口が渇く、水分をたくさん飲む、おしっこの量が増える、体重減少、全身がだるい、脱力がある、動悸がする、たくさん汗をかく、多尿、浮腫、血圧高値、頭痛、色素沈着、多毛、骨粗鬆症など
診療実績
|
R4年度 (2022年度) |
R5年度 (2023年度) |
R6年度 (2024年度) |
|
|---|---|---|---|
| 外来延患者数 | 12,074人 | 13,379人 | 15,677人 |
| 入院延患者数 | 1,901人 | 2,146人 | 2,125人 |
| 1日平均外来患者数 | 50人 | 56人 | 65人 |
| 1日平均入院患者数 | 5人 | 6人 | 6人 |
| グルコースモニタリング | 55件 | 71件 | 48件 |
|
グルコースモニタリング (在宅自己測定)延べ件数 ※令和2年度診療報酬改定より適応拡大 |
292件 |
480件 |
837件 |